こんにちは。門真市会議員団です。
No.2564(2025年8月31日号)
[2025.8.29] -[門真民報]
参議院選挙後初めての定例会
市民の暮らし優先の市政運営を
第3回定例会に提出予定の議案が公表
9月5日に開会予定の第3回定例会(9月議会)に提出予定の議案が、25日に開かれた庁議で決定され、その後議員に対し議案説明が行われました。
提出予定議案の特徴を所管の委員会ごとに見ていきます。
【総務建設】
条例案件では、「門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正」と「門真市職員の育児休業等に関する条例の一部改正」では、現在の部分休業「1日につき2時間を超えない範囲」で取得する方法に加えて、新たに「1年につき77時間30分を超えない範囲内」で取得する方法を追加し、職員がそのいずれかを選択できるように部分休業の取得方法を拡充するものです。
職員にとって制度の
拡充ですが、今後は職員の体制確保を進めることがあわせて重要となっています。
この他、「門真市議会議員及び門真市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び門真市議会議員及び門真市長選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正」については、選挙用ビラ及びビラの単価を引上げるものです。
令和7年度一般会計補正予算では、普通交付税の追加6億3538万1千円、前年度繰越金(令和6年度黒字分)の財政調整基金への積立2144万6千円、公金収納の一部デジタル化に伴うシステム改修に1529万円を増額するなどの補正の一方で、古川橋駅北側で建設されようとしている建物の遅れによる密集市街地整備事業の4835万円の減額などが計上されます。
まちづくりでは、41階建てのタワーマンションへの45億円助成金問題に対し、質疑すればするほど問題点が明らかとなり、委員会で徹底審査が求められています。
【民生水道】
民生水道常任委員会所管では条例案件はありませんが、「民事調停の申立て」では、門真市立総合体育館のメインアリーナ床面に発生した損傷に対する損害賠償請求として、相手方に対し、体育館の改修工事に係る費用等(約1億円)を支払うことを求め民事調停を申し立てるものとなっています。
補正予算では、古川橋駅北側に整備が進められている生涯学習複合施設「KADOMADO」に設置する知育玩具や遊具を購入するにあたり、専用サイトを活用したクラウドファンディングを実施するための手数料194万円が計上されます。
また、四條畷市環境センターに市のし尿処理を委託するために令和6年度に支払った四條畷市環境センター運転管理負担金について、実績に基づく精算に伴い歳入として768万9千円、くすのき広域連合解散に伴う事務承継負担金について、実績に伴い歳入として1042万9千円が計上されます。
この他、令和8年5月に予定されている市民課の中町ビルへの移転に伴い、戸籍システム危機を移転するための費用163万8千円が債務負担行為として計上されます。
民生水道所管では、全国で3番目に高い高い介護保険料問題、「マイナ保険証」の押付け、水道事業の大阪広域水道企業団との統合協議など、問題は山積しており、徹底した審査が求められています。
【文教こども】
文教こども所管では、「動産の取得」では、令和8年度開校予定の門真市立水桜学園の家具・什器等の取得が2億3100万円、児童・生徒用机及び椅子の取得が1539万7778円となっています。
条例案件では、「門真市乳児等通園支援事業の整備及び運営に関する基準を定める条例の制定」は、児童福祉法の規定に基づき、「こども誰でも通園制度」(乳児等通園支援事業)の創設に伴い条例を制定するもので、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる通園制度ですが、保育の質の低下等が危惧されます。
「門真市幼保連携型認定こども園条例の一部変更」は、門真市立上野口保育園の移転に伴う名称及び位置の変更。「門真市立学校設置条例の一部改正」は、北巣本小学校を廃止し、四宮小学校の名称及び位置の変更等を行うものです。
この他、補正予算等もあり、慎重審査が求められますが、党議員団は文教こども常任委員会の所属議員がいないことから、開会日の本会議での議案上程の際の質疑を予定しており、しっかり審査していきます。
お金じゃない、人間として扱ってほしい
~生活保護をあたり前の権利に~
第16回生活保護問題議員研修会ー豊北議員ー
「第16回生活保護問題議員研修会」が名古屋市ポートメッセなごや・コンベンションセンターで開かれ、豊北ゆう子議員が参加しました。「地域から変えるー生活保護をあたりまえの権利にー」をテーマに5人の講師が講演し、その後、各地の取り組みなど参加者交流会も行われました。
公平な保護制度の
実現に向けて
桜井啓太 立命館大学准教授は、「データが語る生活保護行政の実態~自治体の運用格差とその影響~」と題して講演。生活保護制度は法定受託事務として、その実施運用には画一性が求められる。実際の運用は実施機関(自治体、福祉事務所)に委ねられていることから、実態として自治体格差があると指摘しました。
群馬県桐生市では50代の受給者に対し、市側が毎日ハローワークへ通うことを条件に一日千円ずつ支給している事案が告発され、本来男性の生活扶助費が半分以下の3万円しか受け取れていなかったことが発覚。調査の中で桐生市では2011年をピークに受給者が半減していることや数々の違法な・不適切運用の疑いが見えてきました。桐生市以外でも連続餓死・自死事件が生活保護行政の中で起こっている自治体についても示しました。
桜井教授は生活保護の相談・開始等の状況を可視化しデータから見えてくる課題を共有することが重要だとし、公平な保護制度の実現に向けて議員の役割が期待されるとしました。
生活保護基準は社会保障制度の物差し

吉永純 花園大学教授は、「生存権を取り戻すとき」と題して講演。米や野菜など急激な物価高騰に賃上げや年金の引き上げは追いつかず、最後のセーフ定ティネットである生活保護基準に至っては、ここ10年来大幅な引き下げが続き、2025年度はわずかな月500円アップにとどまっている。保護利用者は厳しい生活を強いられ、利用者も減少の一途をたどっている。生活保護基準は「生活の土台」で、就学援助など少なくとも47の社会保障制度の物差し(ナショナルミニマム)だと指摘。保護基準の引き下げは利用者200万人に加え、市民生活に多大な影響を与えたとして「就学援助は2023年度で利用児童数が122万人余り。至急、各自治体での影響を調べてほしい」と参加者に求めました。最後に、どうすれば生活保護制度を暮らしに役立つ制度にできるのか、地方議員の出番と述べました。
不適切な運用をなくすことを議員に期待
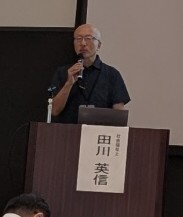
生活保護問題対策全国会議事務局次長の田川英信さんは、最後のセーフティネットの生活保護が権利になっていないとし、①生活保護バッシング等で忌避感が強い②水際作戦(違法・不適切な対応)③生活できない保護基準等をあげ、福祉事務所での人権擁護に立った研修体制の拡充等を求めることを訴えました。
自動車保有の改善を
日弁連貧困問題対策本部事務局次長 太田伸二弁護士は、生活保護での自動車の保有・利用は極めて厳しく制限されているため、生活保護を利用するうえでの高いハードルになっていると述べました。 三重県鈴鹿市の裁判や運動の結果、保有が認められた自動車の利用については、大幅な緩和を勝ち取ったことを詳しく述べ、今後の自動車保有を制限する制度運用の将来に見通しが持てる保護基準に改善についても述べました。
将来に見通しが持てる保護基準に

日本女子大学教授の岩永理恵氏は、ナショナルミニマムとしての生活保護基準の歴史とあるべき姿と題して講演。岩永氏は生活保護行政の現状(過払いや未支給等)、保護基準額表の複雑さ(ケースワーカーが理解できているのか)、最低生活の貧しさについて述べ、「利用者が将来の見通しを持てるくらい充実させなければいけない」と指摘。保護基準を定める新たな算出方法を提案、改めて最低生活とは何かを考えていく必要があると述べました。
いのちのとりで裁判
弁護団・原告報告
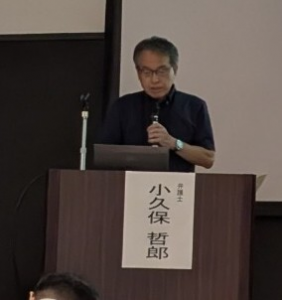
講演の最後に、史上最大の生活保護基準引き下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判全国アクション」事務局長の小久保哲郎弁護士から報告。全国29都道府県で千人を超える原告が立ち上がり31の集団訴訟で闘ってきたことを振り返り勝訴の判決を勝ち取ったことの喜びとともに詳細について報告しました。愛知県の原告の方からは、「飢えと暑さで生き地獄、偽装で命を削られた。お金じゃない人間としてあつかってほしい。各議会で訴えてほしい」と思いが語られました。今回の研修を受けて、今後も、本市の生活保護行政の実態と改善に向け議会で取り組んでいきます。

